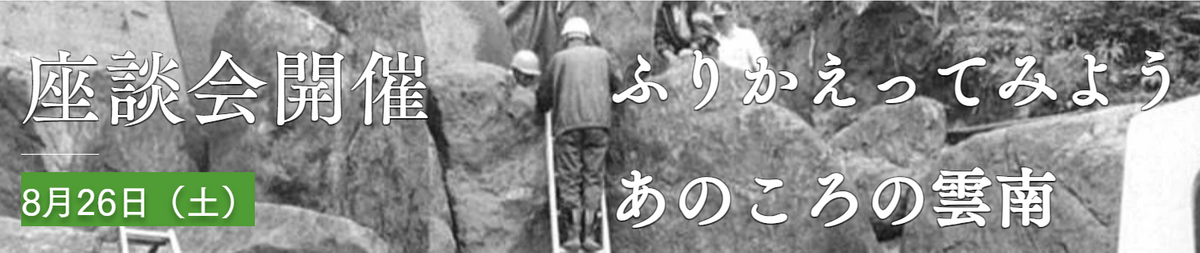御礼
2023年10月吉日
「石照の庭」出版プロジェクトにご賛同いただき、本当にありがとうございます。
原稿はそろったものの、果たしてどうやって出版したものか、悩む日々でした。できれば出版したことをゴールではなく、スタートにしたいと思っていたからです。
本の主人公、堀江洋伸は、筆者でこのクラウドファンディング依頼者の実父です。子どものころから、テレビに映る「一般的な」父親像と違って、会社に通うわけでもなく、スーツを着て出掛けたかと思えば、地下足袋姿でトビ口を持って山に行き、枝打ちや間伐、果ては何トンもある石材を運び……。
「いったいあの人は何者?」という父の仕事が、社会に対して果たしてきた役割とは、そして今の広がりとは?をうかがうクラウドファンディング募集でした。
8月26日に座談会を開きましたときに、パネル写真を指さしながら、一緒に植林のために山に登ったことを懐かしがったり、またその写真の当時は子どもだった人たち同士が、楽しそうに語り合っていらっしゃる姿をみて。また話がとってもよかったと言ってくださる声を聞いて、意義のある時代、戦後をつくった人々は、いまにつながるたくさんのよい仕事をしてきたのだと実感させてもらいました。
こうしてたくさんの応援をいただき、やはり出版の意義はあると認識した次第です。小さな出版ではありますが、あすの出雲・雲南をつくる一歩につながることを願って、出版にゴーをさせていただきます。感謝をこめて。

活動報告
〇成果
書籍を読んだ方より、下記の言葉をいただきました。
『「父母も その父母もわが身なり われを愛せよ われを敬せよ」(二宮尊徳)が気に入った。自分はこれを書で、横田の展示会に出す。』
私もふと思い出しましたが、この通りで、自身と先人を敬することがつながり、自分を大切にしたいと思います。
プロジェクトの感想としては、読者から先祖とのつながりについて話をいただくことがあった。また事業経営についても、書籍の感想を述べたうえで、私の組み立て方からアドバイスをいただくことがあり、ありがたいと感じています。
取材対象の堀江洋伸さんがすこぶる元気になり、また自分の健康を気遣うようになりました。90歳を迎えようとするご本人が再度、縁のあった人たちとコミュニケーションをとり、語らいあっていることが、これが健康の秘訣だとも感じました。ひとつの成果ではないでしょうか。
「余生ということは存在しない。年寄りの価値は経験が語れることであり、若者はそれを聴く。自分のために。そうすれば余生という概念はないのだ」という言葉を聞いたことがあります。先人のことを探るのは、つとに自分のアンテナが問われるのだ、今後の事業の展開のために。
〇プロジェクトを行った所感
・書籍という形をとっているので、私も含めて読者にとっては心のなかに再生産ができる。書棚においていただければ、また手に取っていただける。
・長い歴史があるこの国にとって、総力戦と多くの死を経た敗戦後の昭和は、やはり国として青春であったのではないか。その一つのケースを記したのが、この書籍と感じている。
・いま「元気を出せ」というが、日本各地の先人がつくった「戦後民主主義」は、終わったことなのだろうか?われわれは本当に成果物として受け継いでいるのか?
・いま日本社会の活力を思うとき、生活の豊かさはあったとしても、21世紀中盤を臨むにいたっても戦争が続き、核拡散の恐怖がある世界の現状を直視すべきだ。20世紀の問題はつづき、広がっており、それはこの国に生きる人たちにとって、最前線の問題でもある。ですから、平和と民主主義は今の問題で、書籍のテーマは過去ではなく、いまに続き、地域からグローカルにつながるはず。
〇今後の予定
今後は、出版を受けた広がりを期待しています。シンポジウム等々を考えたいですが、読んでいただいた方の反応をまって計画していきたいです。雲南から普遍的な問いを広げる、きっかけになることを願っており、そのための一歩としたいと考えています。
ご支援・応援をありがとうございました!
〇今後の活動はこちらからご覧ください!
HP:https://www.sekisho-teien.com/
Facebook:https://www.facebook.com/Sekishoteien
Instagram:https://www.instagram.com/sekishouteien/
書籍「石照の庭」出版に向けたご挨拶
並びにクラウドファンディングのご依頼
1934(昭和9)年生まれ。終戦から青春時代が始まり、時代とともに広い田畑を少しづつ庭に変えていったひと、堀江洋伸の人生を、青年団活動、38豪雪、水害、ダム移転…と、この地で暮らした多くの人々の暮らしと重ねながら追う本を作りました。出雲地方に暮らす人々、特に昭和を味わった方々に、語り合っていただけるネタ本になることを願っております。書籍は郷土出版という形で、地域の記録として、書店、図書館等で手にとっていただけることを目指しておりますが、出版資金面で苦慮しております。皆様のご協力を、心よりお願いします。
石照庭園 堀江研次
文化のるつぼのような都会で楽しく過ごしていたのも束の間、わたくしは1995年に島根に帰郷しました。その年は1月の阪神淡路大震災、3月の地下鉄サリン事件と、バブルの残り香を瞬時に消し去るような大災害とテロが立て続けに起こるなか、地元ローカル紙に職を得て、取材、広告依頼、配達、配送と、およそ「新聞ってどうやって作るんだっけ?」をトコトン実地で教えていただいた……日々を過ごしました。綾小路きみまろさん、ではないですが、「あれから30年!」。その間のメディアと通信の変化の波は、わたくしの編集スキルを元のスタートラインに押し戻してしまい、今、わたくしに残っているのは、思い出深い、何人もの方々から教えていただいた「人生の味」でした。中年(ちゅうねん)、と言われる齢を迎え、ひるがえって、わたくしにはどんな味があるのだろう?と立ち止まりました。人に語って、「おいしいねえ」と思ってもらえる味があるのだろうか?わたくしのソンザイイギって???
この「四十代の自分探し」は、父母の人生を聴くことから始まり、またその縁のある人に聞いて事実確認をとり、やがて祖父母、その親、またその家族……とさかのぼってゆき、面的には、ふるさと、その山河、戦争…、たたらに象徴される江戸時代の産業、そして戦国の戦い、と、時空を超えて広がっていきました。いまその途中経過をまとめ、書籍という形で読んでいただくよう、制作しています。かつて本の編集を担当したことはあるのですが、いざ、自分で執筆となると、多くの時間と労力がかかるもの、と思い知らされました。
そして出版社・報光社のお力と、ご協力いただいた方々のご尽力により、出版にはあと1センチのところまでたどり着きました。この1センチが困難なものと覚悟しているところです。
「ジブンを探し」は、若者だけの特徴でしょうか?願わくばクラウドファンディングを通じたご協力を賜り、接著「石照の庭」を読んでいただいて、
「あのころ」
「ジブンはいなかったけど、あなたがいなければ確実にジブンにたどり着けなかった、あのころ
「あの場所」
の、時空の旅に出発してもらえれば、とてもうれしいのです。などと、気負いながら、しかし、しかし、あと一センチ、押しやってくださいませ。
心より、ご協力をお願い申し上げます。
石照庭園について
室町南北朝の時代に近江から出雲に移った堀江家。古い歴史をつむぎ、近代の荒波にもまれながらも、二十三代、堀江洋伸が二十代からコツコツと築庭していった庭を2000年より観光日本庭園として開園いたしました。園は水を生む背景の石王山も含めて、2ヘクタールに及びます。大池を囲む巨石の滝組みをめぐりながら、ひととき庭園文化を全身で浴びていただける空間を用意しています。
プロジェクトについて
2016年、著者の高齢になった堀江洋伸氏のインタビュー・ヒアリングから始まりました。松江からライター建岡さんに半年ほど何度も足を運んでいただき、当時は存命だった母・堀江澄子も一緒に音声テーブに収まって、膨大なテープ起こしをしていただきました。
執筆は母の逝去を経て、それをもとに2017年末から始まり、広島市、呉市、津和野町など関連地の取材と、年代の確認、書物や、特に戦後すぐの、新たな青年運動、教育運動など、ヒアリングに出てきた人々の確認に多くの時間を割いています。書籍は出雲市の出版社・報光社さんのお力を経て、また、協力いただいた古浦義己先生、交易場修先生に校正をいただいて、今2023年7月現在、六校まで仕上がっているところです。

昭和39年、赤川堤防決壊から立ち上がった文房具店仮店舗、まだまわりにがれきが見える
目指すこと
なぜプライベートな物語を広く読んでいただくのか?戦後、苦しかった時から、昭和元禄といわれるとき、また、世界のなかで日本の立ち位置を巡って揺れる平成にいたるまでの時代を、出雲というフィールドと主人公を、物語を読み進める中でなぞることによって、ある種の普遍性が生まれることを狙っているからです。
物語はこの“雲南”をフィールドに、近江から出雲に至る600年の系譜も探します。そのなかに尼子、毛利、三沢と、ここを活動してきた先人について、堀江家を通じてわかる点について表記しました。一緒に、室町から現代にいたるときを自由に行き来してもらえればと思います。
費用の一部を援助いただきたいのはもとより、クラウドファンディングを通じて「みんなでつくった本」「おらの本」といっていただける書籍を目指したいです。書籍は出版社と最終調整に入っています。クラウドファンディングを通じて出版資金の目処が立ち次第、装丁等を決定し、印刷製本、そして書店、ネット書店を通じて秋から配本します。

昭和38年豪雪で雪をかぶった機関車
寄付の使途
島根の出版社、株式会社報光社から出版します。出版のための費用に充当させていただきます。
返礼品について
05,000円~9,999円:出版した書籍をお贈り致します。(2023年秋予定)
10,000円~00,00円:出版した書籍をお送り致します。併せて、書籍にご協力いただいた方としてお名前を掲載させていただきます(ご希望者のみ)。
メンバー・応援者からのメッセージ
交易場修さん:元けやき出版(東京都)編集長
庭師・堀江洋伸さんから「地域にかつての賑わいを取り戻すために、石照庭園を始めた」とうかがう機会があり、その時すぐ「境地」という言葉がひらめきました。詩、絵画、演劇、作庭等々、様々な手段を通じてほとばしる表現欲求。時代の変化と生活の必要に応じた判断を積んで歩いてこられた道。この伝記に描かれている人生の底に、「表現者・堀江洋伸」が常在していることに気づかされます。若年の頃より一貫している表現欲求に、時の経過にともない、たとえば「地域への貢献」という「信念」が重なり、「境地」と呼ぶしかない次元に昇華されていく。その道程を目の当たりに出来るのが、本書です。

古浦義己さん:文藝雲州編輯室
『石照の庭』は優れた庭師堀江洋伸さんの自伝であり、木次町の風景に似合う「石照庭園」を造った経緯も書かれた貴重な一冊です。この書を手に庭園を巡れば、滝の流れ、白い土蔵や観音堂が心地よいひと時を感じさせてくれます。

寄付者様からのメッセージ
【NALU助産院様】毎月はぐもぐ食堂を開催させてもらっている石照庭園様。四季折々の豊麗な景色を贅沢に楽しませてもらっています。庭園を起点に、紐解かれる歴史、発刊楽しみにしてます。クラファン頑張ってください♪
◆民俗学の貴重な史料として絶対に学術的な価値があると思います。是非大学との連携を進められて、島根県の財産にされることをお祈りしております!(雲南市 М様)
◆書籍の完成楽しみにしております‼︎(雲南市 Y様)
◆地域の歴史・先人たちの想いを知ることができる貴重な書籍を作ってくださってありがとうございます。(雲南市 M様)
◆本の完成楽しみにしてます(神奈川県 S様)
◆いつもお世話になっております。微力ながらお手伝いさせてください(雲南市 H様)
◆僅かで申し訳有りません。書籍出版楽しみにしています。(雲南市 W様)
◆執筆時のこと、出版されてからのことなどぜひお話を伺いたいと思います。感動と熱量の共有をお願いします!(雲南市 S様)
◆雲南市の歴史を伝える大切な本だと思います。ふるさとへの思いは誰もあると思います。雲南市であれ、奥出雲町であれ、どの町でも生まれ育った場所がある。古き歴史もある町から巣立つ者もいる。でも生まれ育ち巣立ったものはふるさとへの思いがある。生まれたふるさとへと思いを恩返しとしてこの本を手に取り、その頃何があったかを見て学んでほしい。そして、次なる世代へと継承。、大人から子供へと語りついでほしい。(雲南市 U様)
◆地域発展のため益々ご活躍を!(雲南市 S様)
インタビュー動画
みんなでカンパに挑戦中の「雲南に生きる」出版プロジェクト堀江研次さんにプロジェクトへかける想いを伺いました。
インタビュー① 石照庭園と堀江研次さんの紹介
インタビュー② プロジェクトで製作中の書籍「石照の庭~庭師・堀江洋伸の歩んできた道」について
インタビュー③ みんなでカンパへの想い
8月26日(土)10時より石照庭園にて 座談会「ふりかえってみようあのころの雲南」開催がありました。 当日の様子をYouTubeで配信されています。こちらからご覧いただけます。